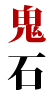少年も先ほどまでいた地味な女が、本来こんな姿をしているとは思ってもいなかったのだろう、唖然としている。
いきなり紅姫という刀が出てきた理由はわからない。
だけど…
「私はこんなところで死ねないから…。」
戦うしかないんだ。
鈴音の言葉で少年はハッとし、我に返った。
「“神器紅姫”…××か…。フン面白い。お前を殺したら何色になるのか興味がわいた。」
「うるさい!」
鈴音は刀を少年に向かって振る。
少年は華麗によけるが、切羽が詰まっているような表情をした。
そして何回かの攻防を繰り返していたとき、少年の顔に1つの切り傷ができた。
「チッ」
少年は受けの構えをとっていた刀を鞘に戻した。
「何をしてる…」
「お前だけが優勢に立ったと思うな!我の声に答えよ!神器橙玉(とうぎょく)!」
さきほど鈴音が紅姫を出したときの赤い光と同じように、オレンジの光が現れる。
そして少年の手に日本刀を象った。
「“神器”を使えるのがお前だけだと思ったか!」
かわらない。武器が変わったからって形勢は変わらない…
『鈴音、受けの構えをとって。』
(ううん。いけるわ。私は怪我なんてしないから攻めなきゃ…。)
『だめ!前!』
「え?…っ!!」
前を向くと少年の刀の刃が顔のすぐ横にきていた。
少年と同じところに切り傷がつく。
大丈夫、大したことない。
これくらいならすぐに治…え?
「治らない…!?」
頬を赤い液体がつたった。
「お前が考えていること、あててやろう。自分はそんな小さな怪我なんて数秒あれば治る。なのになぜ治らない?違うか?」
少年の言ったとおりだ。
“九条鈴音”の“異常”なことの1つ。
怪我が常人の何倍ものスピードで治ることだ。
だが致命傷は治るのかはわからない。
そんな傷おったことないから。
「なんであなたがしってる!」
「俺はお前と同じだからだよ、鈴音ちゃん?」
クスクスと笑う声がはらわたを煮え繰り返す。
どういうことだ。
彼も傷がすぐに治るのか…?
「俺たち“鬼”は傷や病では死なない。ただ1つ“神器”で心臓を貫かれない限り、な。」
鬼…?
「何を言っているの…?」
「何も知らずに育ったお前にはわからないよ。まあ言えることは、今この場では、お前は俺を殺すことができるし、俺はお前を殺すことができる。」
もし仮に彼が言っていることが正しいとしよう。
私や彼は“神器”と呼ばれるものでしか殺せない。
そして私と彼は“神器”と呼ばれるものであろうものを持っている…。
ただ事実だという確証はない。
嘘だという確証もない。
「余所見してていいのかっな!」
少年が神器を振り上げる。
間一髪のところで鈴音が受けの体勢をとる。
「なんでそこまでして私を殺そうとするのよ…」
「俺、一度殺すって決めたものはどんなやつでも殺すんだ。たとえそれが親でも兄弟でも親友でも恋人でもね。」
「…っ!」
二人は神器で攻防を繰り返す。
そろそろやばい…。
体力がもうない…。
殺される…
一瞬生きることをあきらめた。
もう殺されてしまう、そう思った。
その瞬間脳裏に今まで生きてきて一番後悔したときの映像が流れた。
『鈴音ちゃんはいいね、私も鈴音ちゃんみたいになりたかったな…』
『まって!ダメ!×××!』
『バイバイ…。鈴音ちゃんは生きて、ね。』
世界で一番好きだった人が世界から消えた瞬間。
私はこんなところで死なない、生きなきゃ…
「我の声に答えよ!神器翠憐(すいれん)!」
そのとき、少年でも鈴音でもない第3者の声が響き渡った。
そして緑色の光が現れ、彼が姿を現した。
「近衛…くん?」
鈴音のクラスに来た転校生、近衛椿だ。
「おい、殺人鬼。こんなところまではるばる来てやったぞ。感謝しろ。」
椿は学校のときとは全く違う目で少年をにらみつけた。
「これはこれは近衛の当主様。追いかけてきてもらえるとはね…。」
少年は軽口を立ていているようだが、深刻な顔をしていた。
「いくらお前でも神器所有者2人の相手はきついだろう?」
椿が意地悪そうに言う。
「…そうだな。じゃあ今日はここら辺で閉幕といたしましょう。それでは若当主。ご武運を。」
軽い一礼をしたかと思うと少年の姿はそこになかった。
終わったの…?
あれ…世界が…回ってる…?
鈴音の意識はそこで途絶えた。
「おい!おい!大丈夫か!?…気絶しただけ、か。はぁ…。」
椿は鈴音を抱き上げて商店街を離れた。
───────────────────────
←戻る 次へ→