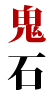“普通”って何だろう。
可愛くもなければブスでもないことかな…。
頭がいいわけでもなければ悪いわけでもないことかな…。
漫画やアニメの主人公みたいに“特別”じゃないことかな…。
「わかんないよ。」
───────鬼石────────
朝8時半。
登校時刻をまもなく迎える、国立鬼灯(ほおずき)学園高等部の廊下はにぎわっていた。
このにぎわっている時間に、真っ黒の髪を低い位置で二つに結び、ふちなし眼鏡をかけた地味な女子生徒が1人登校してきた。
あまり目立たないように登校するのが彼女、九条鈴音(くじょうすずね)の日課となっている。
「それでね…あっ九条さん。おはよう。」
「おはよう。」
廊下ですれ違う顔見知りに当たり障りない軽い挨拶をして教室へと入っていくのも彼女の日課だ。
教室に入り窓際一番後ろの席につく。
今日も普通に過ごせそうね…。
そんなことを考えながら鈴音はぼんやりと窓の外を眺めていた。
「鈴音、おっはよ。」
黒い短髪に小さめの背。
「おはよう日向くん…。」
鈴音のクラスメイトであり親戚の藤堂日向(とうどうひなた)だ。
親戚といっても、鈴音の母方の伯母の旦那の弟の息子、ややこしいが血は繋がっていない。
鈴音がこの町にやってきた中学3年のときからご近所さんということでたまにお世話になっている。
「母さんがコレ、鈴音に渡してってさ。」
日向はポケットからメモ用紙を取り出し、鈴音に渡す。
「苺ジャムの作り方…あ、ありがとう。これ日和さんに頼んでたの。ありがとうって伝えて。」
日向の母である日和は、鈴音とはまったくの赤の他人であるが、随分と親切にしてくれている。
以前彼女の手作り苺ジャムの味に感動して、レシピを教えてくれと頼んでいたのだ。
「了解。」
そういって日向は仲のいい目立った男女グループの輪に戻っていった。
今日は苺をたくさんかって、パンとかも買っていこうかな。
明日からのおやつや朝食を想像していると、盛大な音をたてて扉が開いた。
「お前らー席つけー。今日は割りと忙しいから早くしろー。」
やる気があるのかないのかいまいちわからない声が教室に響き渡った。
担任の安田葛(やすだ かずら)だ。
160ギリギリあるかないかの低身長で、整ってはいるが童顔というなんというか天はニ物を与えないとはよく言ったものだと感心する。
「おーい。近衛(このえ)くーん。入っていいぞー。」
葛が、相変わらずの調子で扉の向こうにいる誰かに声をかけた。
「はい…。」
葛にあきれているのか少し苦笑いで1人の男子生徒が現れた。
彼が教室に一歩入ったとたん、教室中の秩序が乱れたのがわかった。
少し緑がかった髪と目で端整な顔。
いわゆるイケメンという分類に入るだろう男子が教室に入ってきたのだ。
「うるさーい。あー今日からこのクラスの仲間になる近衛君だー。はい、近衛君、自己紹介。」
「はじめまして、近衛椿です。家の都合で転校してきました。わからないことだらけなので教えてくれるとうれしいです。これからよろしくお願いします。」
椿は少しだけ口角をあげ、優しそうに笑った。
「ねえねえかっこよくない?」
「やばいね、ついにこのガリ勉高にイケメンが!」
クラスの女子たちは椿の笑顔で盛り上がっていた。
ただ1人、鈴音を除いて…。
鈴音は相も変わらず空を眺めていた。
「…う、九条!」
「はい!!」
ふいに名前を呼ばれた鈴音は声を裏返しながら返事をした。
「たくー。ボーっとするなよ。せっかくテンコーセーくんが自己紹介してるのに、なあ?」
「いや…」
なあ?と言われても、と椿は困った顔をする。
「すいませんでした…。」
「うーん、九条。お前、近衛の面倒しばらく見ろ。案内とかまかせる。近衛くん、席は九条の左隣な。以上、近衛くんの件について反論は認めん!じゃ、また後でな!」
それだけ告げて葛は教室を出て行った。
ヒソヒソと話を始める女子生徒に、可愛そうな目で見てくる男子生徒、助けたほうがいいのか助けないほうがいいのか迷う親戚、ただ呆然と立ち尽くしている転校生。
…目立ちたくないのに。
近衛が鈴音の左隣の席に向かって歩いてくる。
「えっと…九条さん?だっけ。よろしくお願いします。」
「…はい。」
それだけの短い会話を交わし、二人は席に着いた。
二人が席に着くのを見計らったように教科担当の教師が教室に入ってきた。
───────────────────────
次へ→
Copyright(C)yukine All Rights Reserved.
Designed:LA.